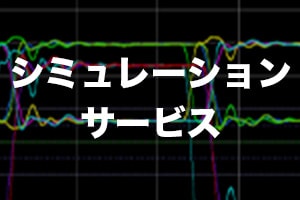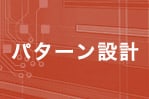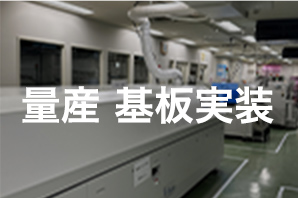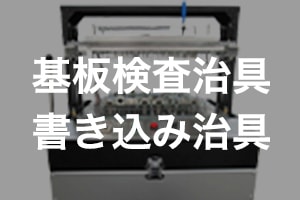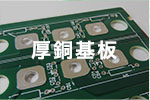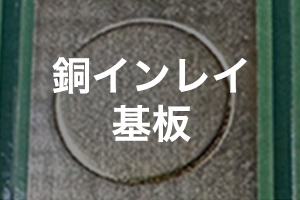GND設計は、ノイズ対策の基盤であり、
基板全体の品質や信頼性に大きな影響を与えます。
GNDは単なる0Vの基準電位にとどまらず、
信号のリターンパスとしての役割に加え、ノイズの吸収やシールド効果など、
多面的な機能を担っています。
しかし、GND設計が適切でない場合には、
・リターンパスの不安定化による信号品質の劣化
・GNDプレーンの分断に起因する予期せぬノイズの発生
といった不具合を引き起こし、回路全体の性能に悪影響を及ぼすこともあります。
そこで今回は「基板品質を高めるGND設計の勘所」と題し、
GND設計における重要な考え方と具体的なポイントを5つに絞って解説いたします。
ポイント①:リターンパスを意識したGNDベタの設計
GNDベタを形成する際は、信号の流れだけでなく、それに対応するリターン電流の経路を確保することが非常に重要です。
特に2層基板では内層がないため、反対面に広くGNDベタを敷くのが難しく、リターンパスを十分に意識したレイアウトが求められます。
また、高速信号ではリターン電流が信号配線の真下を通ろうとするため、その直下あるいは隣接層にGNDプレーンを配置することが有効です。
すべての信号で厳密にリターンパスを確保するのは難しい場合もありますが、重要な信号から優先して設計することで、ノイズ抑制と高品質な基板の実現が可能となります。
ポイント②:GNDベタは“広さ”と“つながり”が重要
GNDベタを広く取ることは、インピーダンス低下やノイズ耐性の向上、さらには放熱性の向上といった多くのメリットがあります。
しかし、広ければ良いというわけではなく、設計時には“つながり”にも注意が必要です。
CADで自動生成したGNDベタには、他のGNDと接続されていない“浮島”と呼ばれる箇所ができることがあります。これらは電気的に孤立し、逆にノイズ源となってしまう場合があります。
対策として、浮島は削除するか、複数のビアで確実に他のGNDと接続しましょう。また、細長いベタ部分にもビアを挿入するか、接続が困難な場合はカットすることが推奨されます。
さらに、基板の周囲をGNDベタで囲むことで、外部ノイズの侵入を防ぎ、内部からのノイズ放射も抑制できます。
ポイント③:クロストーク対策にGNDガードを活用
メモリバスなど、多数の信号線を並行して配線する箇所では、クロストークによる影響が無視できません。
その対策として有効なのがGNDガードです。例えば16bitのバスであれば、4bitまたは8bitごとにGND配線を挿入することで、隣接信号線の干渉を抑制できます。
より強力な対策として、信号線1本ごとにGNDラインを並行して配置する方法もあります。
また、クロックやリセットなど特に重要な信号については、ガード線のパターン幅をビアが配置できる程度に太く設計し、GNDとの接続を確実にすることで、より高い効果が得られます。
なお、GNDガードは単に設ければよいというものではなく、配線幅や接続方法にも配慮した設計が必要です。
>>多数のパターンが並行して配線される場合のGNDガードについてはこちら
ポイント④:パスコン配置時はGNDへの接続を最適化
パスコン(バイパスコンデンサ)は、電源ラインのノイズ除去に不可欠な部品ですが、効果を最大限に引き出すためにはGND側の配線設計が重要です。
GNDは基板全体の電位基準であるため、パスコンは電源とGND間に配置し、そのGND側の接続はできるだけ短く、かつ低インピーダンスであることが望まれます。
とりわけ、電源IC周辺に設置するパスコンについては、ICの電源端子とGND端子を最短で接続するのが基本です。
さらに、パスコンのGND側をGNDプレーンや広いGNDパターンへ直接接続することで、GNDラインのインピーダンスを下げ、ノイズの回り込みを防ぐことができます。
こうした設計により、回路の安定性とノイズ耐性を大きく向上させることが可能です。
ポイント⑤:GND分離時の“一点アース”は柔軟性を持たせる
電源GNDと制御GNDを分離することで、ノイズ干渉を軽減するのは一般的な手法ですが、分離方法や接続ポイントによっては回路性能に大きな差が生じます。
多くのケースでは、電源入力部の電解コンデンサ付近でGNDを分離し、必要に応じて一点接続(一点アース)します。
この接続位置は、ノイズの流れに大きく関わるため、慎重に選定する必要があります。
設計段階で複数の接続用パッドを用意しておき、0Ω抵抗やジャンパなどで接続位置を切り替えられるようにしておけば、評価時に最適なポイントを見極めることが可能です。